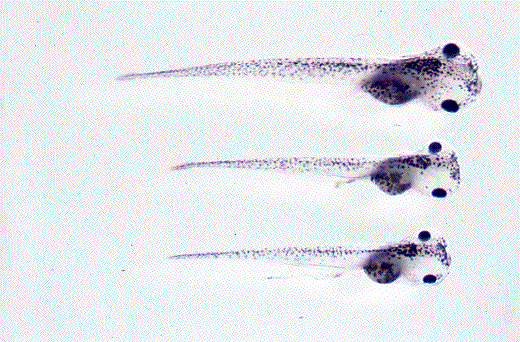
発生における調節機構の研究
発生における調節現象は、ウニ胚を用いたドリーシュの実験(1892)により初めて示されました。彼は、2-4細胞期のウニ胚を各割球に分離したとき、各々が完全な幼生に発生できることを発見しました。ほどなく、両生類胚においても、2細胞期胚の一方は分離すると完全な幼生に発生できることが、他の研究者らにより明らかにされました。
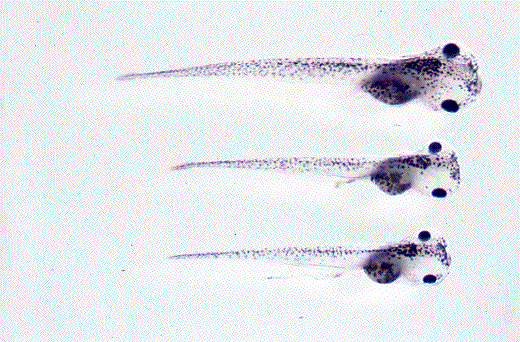
半胚からの発生
対照胚(上)と2細胞期左右半胚から発生した胚(下)
動物の胚はこのような調節的な発生能力を大なり小なり持っています。そして、後口動物の胚は、ホヤのような例外を除き、この能力が高いことが知られています。しかし、調節的な発生を可能にする機構がどのようなものか?と問うと、大部分が細胞間相互作用にもとづくものであるという以上には、あまり具体的に答えることが出来ません。その機構は極めて複雑であろうと予想されます。しかし、通常の発生を可能にする機構は、調節的な発生現象をも説明するものではなくてはならないはずです。つまり、正常発生機構は調節的な発生機構をも包含するものであり、両者は非常に分かちがたいものであると思われます。
発生における調節機構を明らかにするには、まず、調節的な発生現象がどのようなものであるか、十分に調べてみる必要があります。ところが、実はこのような研究は、特に初期発生過程においては未だに非常に少ないというのが現状です。
我々は、次のような観点から、調節現象の記載に取り組んでいます。